多言語サイトを構築する際に必ず検討が必要になるのが「ドメイン戦略」です。単に翻訳したページを公開するだけでは、検索エンジンやユーザーに正しく認識されず、流入や成果につながらないこともあります。どのドメイン構造を選ぶかによって、SEO効果、運用負荷、ブランド統一のしやすさが変わるため、早い段階で方向性を決めておくことが重要です。
本記事では、多言語サイトのドメインを設計するうえで押さえるべき基本ポイント、構造別のメリット・デメリット、さらに運用やユーザー体験に与える影響について詳しく解説します。国際的に成果を出す多言語サイトを目指すならドメイン戦略の理解は欠かせません。
検索エンジンはURL構造を手がかりにして、どの国や言語を対象にしたページかを判断します。適切に設計されていないと、対象外の国で表示されたり、正しい検索結果に出てこないこともあります。さらに、ユーザーにとってもドメイン構造は信頼性や使いやすさに直結します。ドメインは多言語サイトの土台を決める要素といえます。
多言語サイトでよく使われる構造には「ccTLD(国別トップレベルドメイン)」「サブドメイン」「サブディレクトリ」の3つがあります。ccTLDは「.fr」「.de」のように国ごとにドメインを用意する方法で、現地ユーザーの信頼を得やすいのが特長です。
サブドメインは「fr.example.com」のように分ける方式で、一定の独立性を保ちつつ管理を一元化できます。サブディレクトリは「example.com/fr/」のようにディレクトリで区切る方法で、SEO評価を集中させやすいのがメリットです。
ccTLDは現地市場での信頼性が高く、検索エンジンもその国向けサイトだと認識しやすい利点があります。例えば「.fr」はフランス向け、「.cn」は中国向けといった形です。そのため、国ごとに強いSEO効果を期待できます。
一方で、国ごとにドメインを取得・管理する必要があり、SSLやホスティング、更新コストが増える点はデメリットです。リソースが潤沢な大企業や現地法人を持つ企業に向いた方式といえます。
サブドメインは「fr.example.com」のように、グローバルドメインの下で独立させられる点が魅力です。管理画面を分けたり、現地担当チームが自由に運営できる体制をつくりやすい特徴があります。
ただし、検索エンジンからは別サイトとして扱われる傾向があり、SEO評価が分散することがあります。適切な内部リンクやhreflangタグを設定することで、評価の分断を防ぐ工夫が必要です。
サブディレクトリは「example.com/fr/」のように同一ドメイン下に格納するため、SEO評価を一箇所に集中させやすいのが強みです。運用コストも低く、比較的シンプルに多言語対応を実現できます。
しかし、全世界向けの巨大サイトを一つのドメインで運営するため、サーバー負荷や管理の複雑さが増すこともあります。また、現地チームが独自に動かしにくいため、本社集中管理型の体制に向いているといえるでしょう。
SEOにおいては、hreflangタグと組み合わせてドメイン戦略を決めることが欠かせません。hreflangを正しく設定することで、同じコンテンツが複数の言語で存在しても重複コンテンツと判断されず、検索エンジンが適切に振り分けてくれます。
また、国ごとの検索順位を意識する場合はccTLDが強力ですが、グローバル全体で評価を積み上げたい場合はサブディレクトリが有利です。目標市場とSEO戦略をリンクさせることがポイントです。
運用体制によって最適なドメイン構造は変わります。現地法人やマーケティング部門が独自に動く場合はサブドメインやccTLDが合います。逆に、本社一括で管理するならサブディレクトリの方が効率的です。
さらに、広告運用やアナリティクスの計測にも影響します。複数ドメインを運用するとトラッキングが複雑になるため、グローバルで統合的に数値を見たい企業はサブディレクトリを選ぶケースが多いです。
ユーザーにとってもURLは信頼の指標になります。「.fr」であればフランス向けだと一目でわかりますし、「example.com/fr/」でも直感的に理解できます。逆に、わかりにくい構造は不安を与えるため、シンプルで一貫性のあるURL設計が重要です。
ユーザーのIPアドレスやブラウザの言語設定をもとに自動でリダイレクトする仕組みもありますが、誤判定によるストレスを与える可能性があります。そのため、必ず手動で言語切替できるUIを併用することが必要です。自動判別は補助的な手段にとどめ、ユーザーに選択権を残すことが望ましいです。
多言語サイトのドメインは、SEO効果や運用体制、ユーザー体験に大きな影響を与えます。ccTLD・サブドメイン・サブディレクトリのいずれを選ぶかは、自社のリソースと目標市場によって異なります。
どの構造でもメリットとデメリットがあるため、一概に正解はありません。本記事で紹介したポイントを参考に、自社に最適なドメイン戦略を設計することで、グローバル市場での成果につながります。
グローバルサイト構築の専門メディア「デジブラ」では、独自調査により構築実績を有する50社をピックアップ。その中から代表的な3つの構築目的別に、実績の多い会社を選出しています。
本当に優れた製品の実力を
他国の人に伝えたい!

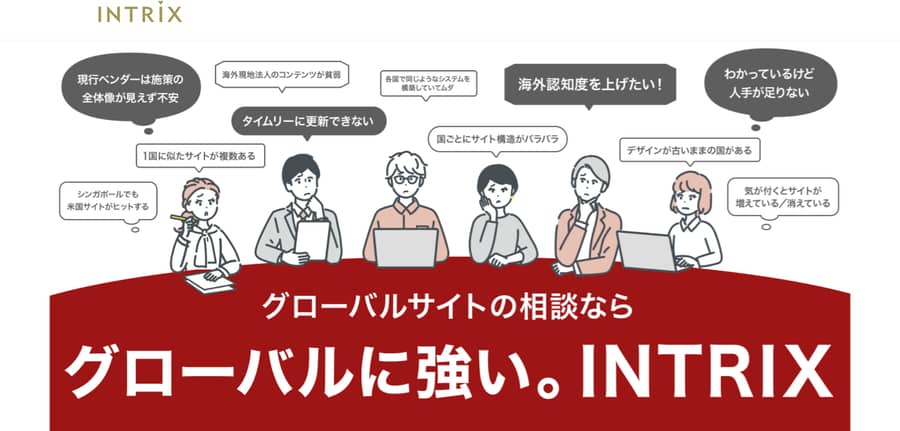
売上規模50億から5兆円のBtoB製造企業170社を支援してきた実績から、BtoB製造業を熟知した会社と言えます。
ローカルサイトも含めた制作・運用を推進できるのが強みで、現地支社を巻き込みながらの進行やシステム構築も得意としているため、戦略立案や企画・プロジェクト運営を相談したいメーカーにおすすめです。
現地の美意識に寄り添い
商材の価値を表現したい!


自社スタジオでの映像制作で、人の美意識に働きかけるような表現を得意としています。
化粧品や装飾品・ファッションなどおよそ30社以上の美容・アパレルメーカーのサイト構築実績を有しており、言語化できない「美しさ」を、映像コンテンツで広く伝えていきたい会社におすすめです。
海外の食文化に配慮しながら
食材の魅力を広めたい!


海外ならではの食文化や、食のタブーに配慮したサイト構築の実績を持ち、大手食料品メーカーからの依頼にも応えられる実力を有する会社です。
成分や栄養価などの情報を、食文化を知るプロが正しく多言語化し、食流通の法規制を守って適切にクリアした上で、ブランド価値を世界中に拡げていく支援に期待できるでしょう。
選定条件:
Google検索「グローバルサイト 構築」の検索結果の165社から、事業としてグローバルサイトの構築を行っていることが公式サイトに記載されている50社を絞り込んだ。(調査日:2024年8月23日)
・イントリックスの選定理由:製造業の海外ビジネス促進を目的としたグローバルサイト構築実績が、50社のなかで最も多い会社として選出。
(※1 参照元:イントリックス サービスサイト|https://www.intrix.co.jp/lp/global-website-strategy/)
・ミツエーリンクスの選定理由:映像やビジュアルを活用したPRを目的としたグローバルサイトの構築実績が、50社のなかで最も多い会社として選出。
(※2 参照元:ミツエーリンクス 公式サイト|https://www.mitsue.co.jp/our_work/projects/past_projects.html)
・あとらす二十一の選定理由:採用強化を目的とした企業サイトを、グローバルサイトとして再構築した実績が50社のなかで最も多い会社として選出。
(※3 参照元:あとらす二十一 公式サイト|https://at21.jp/works/maker.html)