本記事ではグローバルサイトの4つの運用方法について、詳しく紹介しています。それぞれの特徴を把握し、自社に適した運用方法を見出しましょう。海外拠点を展開する企業の担当者の方は必見です。
本社単体運用型は、本社が全てのグローバルサイトや自国のサイトを運用するケースです。元々国内で使用していたWebサイトを翻訳したものをそのまま使用しているため、世界に発信する内容の一貫性を担保できます。
一方で世界各国の特性に対応できる柔軟性を持ち合わせていないことがデメリットとして挙げられます。しかし比較的リソースを割かずに運用可能なので、スタートアップ企業に多く取り入れられています。
各拠点完全個別運用型は、海外の各拠点にWebサイトの運用を任すケースです。各国や地域ニーズを汲み取った運用ができる反面、各拠点でそれぞれコンテンツ制作を行うため、コスト増になることがデメリットです。
主に、飲食系のEC事業に採用されています。また中には本社の意向に沿わない拠点が出てくる可能性があり、適切なガイドラインやルールを決めることが重要になります。
世界でビジネスを展開するなら、各国の文化や商流に合わせた情報発信が重要。自社サイトをグローバル仕様に再構築するのは、もはや必須と言えるでしょう。とはいえ、達成したい目的次第で構築依頼におすすめの会社は変わってきます。
このサイトではグローバルサイト構築実績を有した会社からピックアップしてご紹介しているので、ぜひ依頼先探しの参考にしてみてください。
各拠点独自運用型は、あらかじめ本社がおおまかな方向性や発信方法の基本型を決め、運用を各海外拠点に一任するケースです。本社が枠組みを取り決めているため、情報に一貫性を保つだけでなく、地域ごとの特性に応じた運用を実現できることがメリットです。
多くの企業で取り入れられているケースであり、個別運用型のデメリットを解消できる運用方法です。
本社統制型は、本社が運用における方針を決め、実際に各国の地域サイトを運用するケースです。全体的に適切なデジタルマーケティングを計画し、情報の内容も一貫性を持たせられます。一方で、地域ごとの特性に柔軟に対応することが難しいデメリットがあります。
比較的リソースが豊富な大企業で採用されており、海外企業の多くは本社統制型にシフトしている傾向にあります。
グローバルサイト構築の専門メディア「デジブラ」では、独自調査により構築実績を有する50社をピックアップ。その中から代表的な3つの構築目的別に、実績の多い会社を選出しています。
本当に優れた製品の実力を
他国の人に伝えたい!

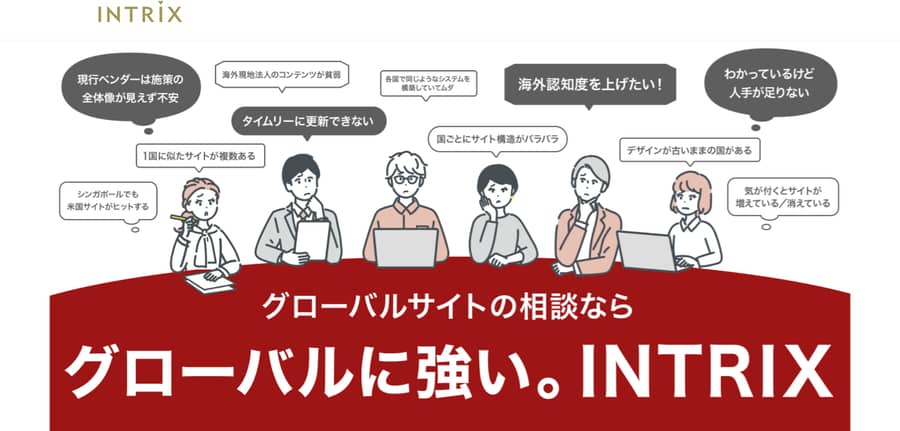
売上規模50億から5兆円のBtoB製造企業170社を支援してきた実績から、BtoB製造業を熟知した会社と言えます。
ローカルサイトも含めた制作・運用を推進できるのが強みで、現地支社を巻き込みながらの進行やシステム構築も得意としているため、戦略立案や企画・プロジェクト運営を相談したいメーカーにおすすめです。
現地の美意識に寄り添い
商材の価値を表現したい!


自社スタジオでの映像制作で、人の美意識に働きかけるような表現を得意としています。
化粧品や装飾品・ファッションなどおよそ30社以上の美容・アパレルメーカーのサイト構築実績を有しており、言語化できない「美しさ」を、映像コンテンツで広く伝えていきたい会社におすすめです。
海外の食文化に配慮しながら
食材の魅力を広めたい!


海外ならではの食文化や、食のタブーに配慮したサイト構築の実績を持ち、大手食料品メーカーからの依頼にも応えられる実力を有する会社です。
成分や栄養価などの情報を、食文化を知るプロが正しく多言語化し、食流通の法規制を守って適切にクリアした上で、ブランド価値を世界中に拡げていく支援に期待できるでしょう。
選定条件:
Google検索「グローバルサイト 構築」の検索結果の165社から、事業としてグローバルサイトの構築を行っていることが公式サイトに記載されている50社を絞り込んだ。(調査日:2024年8月23日)
・イントリックスの選定理由:製造業の海外ビジネス促進を目的としたグローバルサイト構築実績が、50社のなかで最も多い会社として選出。
(※1 参照元:イントリックス サービスサイト|https://www.intrix.co.jp/lp/global-website-strategy/)
・ミツエーリンクスの選定理由:映像やビジュアルを活用したPRを目的としたグローバルサイトの構築実績が、50社のなかで最も多い会社として選出。
(※2 参照元:ミツエーリンクス 公式サイト|https://www.mitsue.co.jp/our_work/projects/past_projects.html)
・あとらす二十一の選定理由:採用強化を目的とした企業サイトを、グローバルサイトとして再構築した実績が50社のなかで最も多い会社として選出。
(※3 参照元:あとらす二十一 公式サイト|https://at21.jp/works/maker.html)